画面が正しく表示されているか
ブラウザをプログラムで操作して、自分の期待通りに画面が表示されるかテストする
コントローラーは正しく動いていても、画面が正しく表示されていない可能性がある
- 画面が正しく表示されているか確認したい
- 画面の表示に必要なデータを作成する
- プログラムでブラウザを操作
→想定どおりに表示されているか確認する
system specを実行できる環境づくり
ブラウザを操作してプログラムを実行できるようにする
パソコンのブラウザを操作するため、ソフトウェアを入れる
brew install cask chromedriver講義の動画ではbrew cask install chromedriverとされているが、現在はbrew install〜の形に変更されている
railsが用意してくれているので、すでに以下がインストールされている
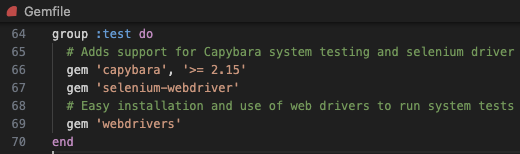
- capybaraは、rubyでブラウザを操作するためのメソッドを提供してくれる
- selenium-webdriverとwebdriversは、rubyからブラウザを操作しやすいようにしてくれている
通常は複数形だが、systemに複数形が存在しないのでこのままでok
次にarticle_spec.rbを作る
記事の一覧がしっかり画面表示されているのか確認する
※コントローラーでテストしたのは、「200が返ってくるかどうか」だけで、表示についてはテストできていない
まずは基本の形↓
require 'rails_helper'
RSpec.describe 'Article',type: :system do
it '記事一覧が表示される' do
end
enddescribe(何についてテストするのか)→'Article'についてテストをするtypeを指定する
→model spec、request spec、system spacでやることが全然違う
→何のテストをするのかrailsに伝える必要がある
Capybaraが用意してくれているメソッド
例えば、visit root_pathと書いてみる
RSpec.describe 'Article',type: :system do
it '記事一覧が表示される' do
visit root_path
end
endこれを実行すると、ブラウザのトップの画面が一瞬開く
bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbブラウザを立ち上げて画面のチェックができるので便利
これまでのテストと同じように、userとarticleを作る
RSpec.describe 'Article',type: :system do
let!(:user) { create(:user) }
let!(:articles) { create_list(:article, 3, user: user) }Capybaraが用意してくれているメソッド
expect(page).to have_content(articles.first.title)該当のページに「articles.first.title」という文字が存在しているかしていないのか判断する
そしてまた実行してみる
bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbするとブラウザが立ち上がり、一瞬だけど記事が3つ表示されているのが見える
そしてテストは成功!(articles.first.titleは存在していた)
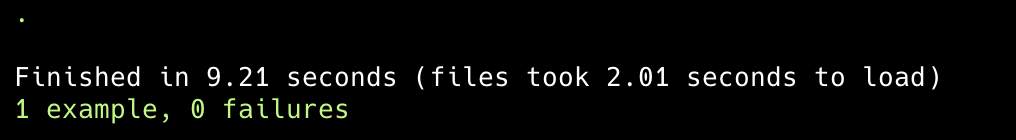
先程は「first」だけだったので、3つともの記事についてテストする
it '記事一覧が表示される' do
visit root_path
articles.each do |article|
expect(page).to have_content(article.title)
end
endテストを実行する
bundle exec rspec spec/system/article_spec.rbテスト成功!
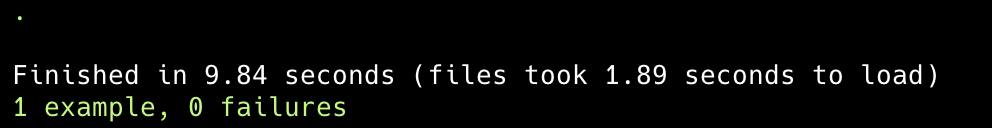
article.titleがページ内に存在するか確かめられた!
・・・でも、存在していても記事のタイトルじゃない可能性がある
(article.titleと同じ文字だからといって、articleのtitleであるとは限らない)
そのため、have_contentだけでは不十分になることがある
#DAY15


